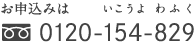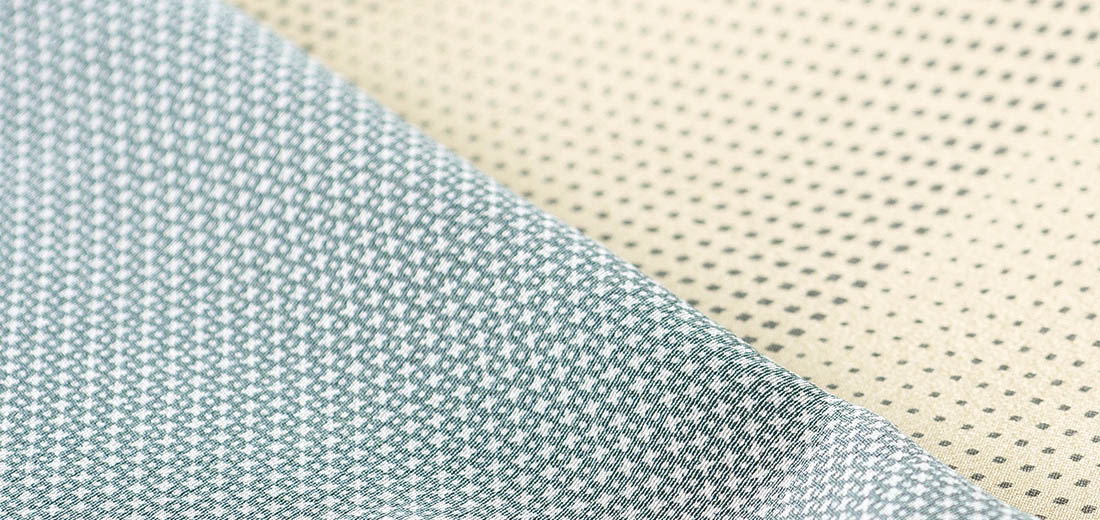霰文[あられもん]
![霰文[あられもん]](/chiebukuro/img/page/monyo04/monyo_13.jpg)
霰が降るさまを文様にしたもの。一見、ごく小さな円形が集まっているように見えますが、実際は円形ではなく、筆の先で押した形です(円形が集まっているのは、水玉文様です)。浮世絵に描かれた女性のきものの文様としても数多く見られます。
鱗文[うろこもん]
![鱗文[うろこもん]](/chiebukuro/img/page/monyo04/monyo_14.jpg)
地と文様の三角形が交互に入れ替わって構成される文様です。魚の鱗に似ていることから付いた名のようです。鱗文には“蛇”のイメージもあり、蛇のように“脱皮するごとに美しく”なろうという意味で、鱗文を長襦袢などに使うこともあります。
立涌[たてわく]
![立涌[たてわく]](/chiebukuro/img/page/monyo04/monyo_15.jpg)
向かい合った曲線で、中央はふくらみ、両端がせまくすぼまった形が連続する文様です。有職文様の一つで、祝儀のきものにも、不祝儀のきものにも使える文様です。
市松[いちまつ]
![市松[いちまつ]](/chiebukuro/img/page/monyo04/monyo_16.jpg)
石畳文(いしだたみもん)のことです。石畳文は、石を敷きつめたさまを表し、四角形を縦横に並べ、一つおきに二色に分けた文様です。八代将軍・徳川吉宗の時代、歌舞伎役者・佐野川市松が舞台で、この文様の袴を用いたことから大流行しました。
竹縞[たけじま]
![竹縞[たけじま]](/chiebukuro/img/page/monyo04/monyo_17.jpg)
縞の一種。竹は、枯れてしまったように見えても、枯れた竹とひと続きになっている地下茎からまたタケノコが出るので、竹林を一つの生命体ととらえると、不死身だということになるそうです。すらりとした姿に宿る生命力にあやかる縞ともいえます。
七宝文[しっぽうもん]
![七宝文[しっぽうもん]](/chiebukuro/img/page/monyo04/monyo_18.jpg)
両端のとがった、葉のような形の長円形を、ひし形につなぎ合わせた形を連続させた文様です。七宝とは金、銀、瑠璃、メノウ、真珠、白サンゴ、水晶のこと。七宝文を良く見ると、丸い宝石が並んで照り輝くさまを抽象的にデザインしたものとも見えます。
雪輪[ゆきわ]
![雪輪[ゆきわ]](/chiebukuro/img/page/monyo04/monyo_19.jpg)
雪の六角形の結晶の形を、円形にまとめた文様です。さかのぼれば、平安時代にすでにあった文様だといわれます。留袖、振袖、小紋、帯と、幅広く用いられる上品な文様です。
紗綾形[さやがた]
![紗綾形[さやがた]](/chiebukuro/img/page/monyo04/monyo_20.jpg)
江戸時代初期に明(みん)から輸入された織物(紗綾)にこの文様が多かったことから付いた名だといわれます。卍の形をくずして組み合わせ、連続させたもので、端正な印象があります。祝儀のきものにも、不祝儀のきものにも使える文様です。